

|

|



 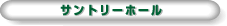
 |
【Aプロ】 2005年4月5日(火)7:00pm
【Bプロ】 2005年4月6日(水)7:00pm
|


思わずほほ緩む近代フランス音楽の花束。タイトルからして情趣あふるるワルツが舞えば、マニュエル・ロザンタールならずともこれぞ<パリの喜び>と膝を叩きたくなる楽の音がこだまする。
満堂のサントリーホールを満たすであろう夢幻の響き、そこはかとなく漂う詩情、鮮烈極まりない激情、そして色彩の乱舞。喝采が早くも聴こえてくるかのよう。
野暮な解説は慎むべきだ。賛辞は尽くされている。
でもステージの主役は、妖艶なドラマを紡ぐミシェル・プラッソンと、ドイツ人の名匠をシェフに戴き成果を挙げつつもフランスの技と誇りを捨てない国立パリ管弦楽団ですよ。しかも彼らが<王道を行く印象派の名曲>という伝家の宝刀を抜くとなれば、普通の誉め言葉では、誉め称えたことにならないのではないか。
南仏トゥールーズ・キャピトル国立管弦楽団の愛すべき総帥と、パリの名門の出逢い。
オペラであれオーケストラであれ、フランスの流儀に寄り添い、そこから導かれる匂やかな触感や発火!の瞬間を愛でるプラッソン。トゥールーズはもとより、パリのオペラ・コミック座で、シャトレ座で、そして東京で、この指揮者は<匂やかな風>をステージから客席に届けた。「スペインの時」の素晴らしかったこと。1933年生まれのパリジャンは、今が最高の聴きどきだ。
一方、ドホナーニやエッシェンバッハと新境地を開拓しつつ、しかし前回2001年日本公演のように巨匠プレートルが指揮台に立てば、摩訶不思議な香気を奏でる国立パリ管弦楽団。
これはもう、ミューズの女神が舞い降り、プラッソンとパリ管弦楽団に「久しぶりに一緒におやんなさい」と微笑んだに違いない。
パリの音楽家の家庭で育ち、ラザール・レヴィやウジェーヌ・ビゴーの薫陶を受けたプラッソンは、トゥールーズのローカル・オーケストラを国立の<世界遺産>に育て上げ、さらにドレスデン・フィル(93〜99年)でも腕を振るい、N響にも客演(73、90、94年)したが、2005年春、いよいよ東京のステージで故郷の名門と再会する。
ルーセル(1869〜1937)の才気がはじけるバレエ「バッカスとアリアドネ」組曲第2番を交えた「ラヴェルな」夕べに心踊らせ、モントゥー、パレー、ミュンシュ、フルネがこよなく愛したショーソン(1855〜1899)の交響曲変ロ長調を指折り数えて待つ。熱烈なワグネリアンにしてフランキスト(フランクの弟子筋)だったショーソンの傑作を、ドビュッシーとラヴェルの名刺曲とともに聴く、しかもプラッソンと国立パリ管弦楽団で聴く−−これを至福と呼ぶ。さあ陽春の匂やかなステージへ。
|