ウィーン国立歌劇場2025年日本公演で、『フィガロの結婚』の指揮をとるベルトラン・ド・ビリー。ウィーンを拠点に、長く活躍しているド・ビリーの功績を挙げ始めたらキリがありません! ここでは2024年から年明け1月にかけて、特にウィーンにまつわる活躍ぶりや情報をご紹介します。
まず2024年12月、ド・ビリーはウィーン国立歌劇場で『ホフマン物語』を指揮しました。ウィーン国立歌劇場におけるフランス・オペラのレパートリーに絶対的な信頼を得ているド・ビリーは、アンドレイ・シェルバン演出による神秘的でシュールな幻想世界を、しっかりと支えました。そして、公演の成功に加えド・ビリーの功績が讃えられることがありました。12月22日の『ホフマン物語』公演後の舞台上で、出演者と観客が見守るなか、ベルトラン・ド・ビリーへのウィーン国立歌劇場の名誉会員任命の授与式が行われたのです。
この栄誉にド・ビリーは「30年前に初めてウィーンを訪れた時、この街がその後の私の人生のあらゆる面でこれほど大きな意味を持つことになるとは、想像もできませんでした。ましてや、1997年1月13日に、かなりの緊張を覚えながら初めて国立歌劇場のオーケストラ・ピットに入ることができた時、そこが私の芸術の故郷になったと言えるようになるとは、想像もできませんでした。私はこれまで世界の主要なオペラハウスのほぼすべてで指揮する機会に恵まれてきましたが、それだけに、ウィーン国立歌劇場のような場所は他にないということを、より一層理解しています。他のどの劇場とも、どの分野の同僚とも、どの合唱団とも、そして何よりも、他のどのオーケストラとも比較できないのです。オーケストラピットに入って、ここで仕事ができることが特別なことだと感じなかった夜は一度もありません。この素晴らしいオペラハウスから名誉会員の称号を授与されたことは、私の人生で想像しうる限り最高の栄誉であり、感謝してもしきれません」と公式にコメントを発表しました。
このウィーン国立歌劇場とド・ビリーの幸福な結びつきが、2024年を締めくくりました。恒例の大晦日の『こうもり』もド・ビリー指揮で上演されたのです。ウィーン国立歌劇場での『こうもり』には、風刺のきいたセリフなどが取り入れられることが多いのですが、大晦日はさらにボルテージが上がります。今回は第3幕で看守のフロッシュがオーケストラピットの演奏者とビゼーの『カルメン』の曲にあわせて冗談を言い合うという場面があったり、オーストリア次期首相の声が高まるヘルベルト・キクルやドナルド・トランプ次期米大統領(2024年12月末時点)のオーストリア訪問に関する皮肉な発言も飛び出したり.....。こうした混乱(?)や皮肉があふれるなか、ド・ビリーはウィーン国立歌劇場管弦楽団とともに、適切かつ新鮮な方法で音楽や作品の魅力を十分に引き出したと評されました。
2025年年明けも、ウィーンではド・ビリーに関わるニュースが発表となります。1月27日に新演出初演を迎える『魔笛』を振ることになっていたフランツ・ウェルザー=メストが健康上の理由により降板することになり、ド・ビリーが指揮をとることが発表されたのが 1月7日のことでした。
新演出のオペラの場合、当然のことながら、再演演目より多くの準備時間がかけられます。この時点での指揮者交代は、劇場にとってもかなり大きなリスクをともないます。ウィーン国立歌劇場総裁のボグダン・ロシチッチも「ベルトラン・ド・ビリーのような当劇場にとって重要な指揮者が、ここで指揮を引き受けてくれることは幸運です」とコメントしています。初演の1月27日はモーツァルトの誕生日。この日に初日を迎えたバルボラ・ホラコヴァ演出の『魔笛』は、3人の少年が幽霊屋敷を発見するところから始まり、登場人物たちと観客が魔法のような世界から現実世界へと旅をしていく...... 絶えず変化する部屋へと移っていくというつくりになっています。ウィーン国立歌劇場において重要な作品の一つである『魔笛』の新演出については、賛否両論が出るのは当然のことですが、ド・ビリー指揮のウィーン国立歌劇場管弦楽団には、「本物のモーツァルトの音色で輝いていた」と称賛する声が多かったようです。
「本物のモーツァルトの音色」って一体.....? と思ってしまうかもしれませんが、ウィーンの人にとっては、"こうあるべき"と誇らしく思っているもの、ウィーン以外の人にとっては、"こうあって欲しい"と憧れを抱くものといったところでしょうか。
ちなみに、ド・ビリーとウィーン国立歌劇場管弦楽団は今年1月19日にはモナコで『ドン・ジョヴァンニ』を演奏しました。演奏会形式と舞台上演の中間的な形式=「空間演出」、ということで、"ウィーンに行かなくても、ウィーンがあなたのところにやって来ます!"と謳った公演でした。この模様を報じた言葉は非常に興味深いものなのでご紹介しておきます。
「ウィーン国立歌劇場管弦楽団に対する最高の賛辞は、それが"ウィーン的"であるということだ。この言葉には、彼らの演奏スタイルを特徴づける優雅さと上品さという概念全体が内包されている。ウィーンでは「Gemütlichkeit」と言う。指揮者はベルトラン・ド・ビリー。彼は前の週にはモンテカルロ・フィルハーモニー管弦楽団を率いてブルックナー第7番を聴かせた。2つのプログラムにおいて、素晴らしい貢献を果たした」(CLASSIQUE NEWSより)
最後に、ド・ビリーという指揮者についての基本情報を。
パリ生まれのド・ビリーは、パリで音楽を学び、オーケストラのメンバー(ヴァイオリン、ヴィオラ)として演奏した後、指揮者になりました。オーケストラ指揮者としてのデビューの後、1991年、26歳でスペインのオビエド芸術祭で『椿姫』を振ったのがオペラ指揮者としてのデビューでした。その後、欧米の歌劇場で活躍していることは周知のところ。1999年から2004年バルセロナのリセウ大劇場の首席指揮者、2002年から2010年ウィーン放送交響楽団首席指揮者、2013年から2015年フランクフルト歌劇場首席客演指揮者、2013年から2016年ローザンヌ室内管弦楽団首席客演指揮者、2014年から2018年ドレスデン・フィルハーモニー管弦楽団首席指揮者を務めるなど、歌劇場およびオーケストラにおいて幅広い活躍ぶりを示しています。
多くの歌劇場やオーケストラと、充実した演奏活動を行えるのは、彼の信条によるところなのかもしれません。インタビューなどが少ないド・ビリーですが、55歳の時に「プレス」紙に「私は作曲家の擁護者です」と題したコメントが掲載されました。4歳にして指揮者になりたいと決意した彼の、音楽への向き合い方のすべてがうかがわれるようでもあります。
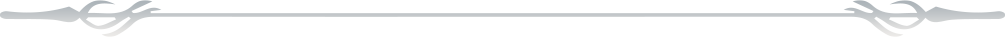
指揮:ベルトラン・ド・ビリー
演出:バリー・コスキー
10月5日(日)14:00 東京文化会館
10月7日(火)15:00 東京文化会館
10月9日(木)18:00 東京文化会館
10月11日(土)14:00 東京文化会館
10月12日(日)14:00 東京文化会館
[予定される主な出演者]
アルマヴィーヴァ伯爵:アンドレ・シュエン
伯爵夫人:ハンナ=エリザベット・ミュラー
スザンナ:イン・ファン
フィガロ:リッカルド・ファッシ
ケルビーノ:パトリツィア・ノルツ
演奏:ウィーン国立歌劇場管弦楽団
指揮:フィリップ・ジョルダン
演出:オットー・シェンク
10月20日(月)15:00 東京文化会館
10月22日(水)15:00 東京文化会館
10月24日(金)15:00 東京文化会館
10月26日(日)14:00 東京文化会館
[予定される主な出演者]
陸軍元帥ヴェルテンベルク侯爵夫人:カミラ・ニールンド
オックス男爵:ピーター・ローズ
オクタヴィアン:サマンサ・ハンキー
ファーニナル:アドリアン・エレート
ゾフィー:カタリナ・コンラディ
演奏:ウィーン国立歌劇場管弦楽団
―平日料金
S=¥79,000 A=¥69,000 B=¥55,000
C=¥44,000 D=¥36,000 E=¥26,000
サポーターシート=¥129,000(S席+寄付金¥50,000)
U39シート=¥19,000 U29シート=¥10,000
―土日料金
S=¥82,000 A=¥72,000 B=¥58,000
C=¥47,000 D=¥39,000 E=¥29,000
サポーターシート=¥132,000(S席+寄付金¥50,000)
U39シート=¥21,000 U29シート=¥13,000
