今秋のウィーン国立歌劇場日本公演に向けて、オペラ・ファンの関心が高まっています。音楽評論家の石戸谷結子さんが、日本公演で指揮をとるフィリップ・ジョルダンとベルトラン・ド・ビリーによるウィーンでの公演の様子を届けてくれました。
ウィーンの春は遅い。雪の降るなか、バル(舞踏会)に明け暮れた日々が終わると、ようやく復活祭の季節がやってくる。今年は4月20日と復活祭が遅いせいか、3月の半ばでも手袋や厚いコートが必須の寒さだった。それでも街の花屋をのぞくと、ネコヤナギや水仙やチューリップの花束が並び、春を告げる日ざしが感じられる。
そんなウィーンで、連日にわたり、素晴らしいオペラ公演を観ることが出来た。『ウェルテル』、フアン・ディエゴ・フローレスがポリオーネを歌う『ノルマ』、『ドン・カルロ』、ネイディーン・シエラとジャビエル・アンドゥアーガの若手コンビが歌う『愛の妙薬』が続けて上演されたのだ。さすがは世界一の"オペラの殿堂"ウィーン国立歌劇場、いずれもとびっきりの大スターが競演する人気演目ばかり。ほとんどが満員御礼の盛況だったが、印象に残った2つの公演をご紹介したい。
プーチン政権への反体制を表明する舞台&映画監督のキリル・セレブレンニコフが演出する過激演出で話題になった『ドン・カルロ』。現代の「衣裳文化研究所」なる場所で、物語が進行する。セレブレンニコフの演出には、大量消費文化への批判や環境問題提起、あるいは宗教戦争や独裁政治批判といった現代の重要問題が重層的に盛り込まれている。ドン・カルロとロドリーゴは「自由」と書かれたTシャツを着て、古い権威主義に断固反抗する。演出意図は充分理解出来、納得もできる良く練られた舞台だが、本来のストーリーはどこへ? という疑問も残った。
ジョシュア・ゲレーロ(ドン・カルロ)とエティエンヌ・デュピュイ(ロドリーゴ)
『ドン・カルロ』(ウィーン国立歌劇場公演より)
Photo: Frol Podlesnyi / Wiener Staatsoper
そんな混沌舞台をしっかりとまとめたのが、指揮のフィリップ・ジョルダンだった。速めのテンポでスピード感があり、音楽に緊迫感がみなぎる。何よりニュアンスが豊かでアリア部分はよく歌わせるし、ドラマティックな盛り上げ方も巧い。全体に高いテンションを維持していくので、少しも飽きさせない。伊語4幕版を一気に指揮する緻密でダイナミックな構成力にも感嘆した。
さらに歌手陣が素晴らしかった。エボリ公女役のエリーナ・ガランチャの圧倒的な歌唱と存在感に加え、ドン・カルロ役のジョシュア・ゲレーロの若々しい声と輝かしい高音にも感服。ゲレーロは東京・春・音楽祭の『蝶々夫人』で来日予定だったがキャンセルした若手テノール。今後は人気が急上昇しそうな期待のイケメン歌手だった。フィリッポⅡ世役のロベルト・タリアヴィーニは美声で美形のバス。ロドリーゴ役のエティエンヌ・デュピュイは昨年英国ロイヤル・オペラの日本公演『リゴレット』で主役を歌ったこれも美声のバリトン。エリザベッタは彼の奥さんニコール・カーと夫妻での出演だ。歌手たちは、歌唱ばかりでなく演技力も抜群。今回の『ドン・カルロ』はウィーン国立歌劇場管弦楽団の絶妙な演奏と巧みな指揮、豪華歌手と斬新演出という、高水準でバランスのとれた公演となった。
ウィーン国立歌劇場は、伝統と革新のバランスが、不思議な調和を見せるオペラ・ハウスだ。古い伝統を大切に護りながらも、斬新な過激演出(『ドン・カルロ』のような)を間に挟み、新・旧の観客を飽きさせない。
ベルトラン・ド・ビリーの指揮した『ウェルテル』は、伝統の重みを感じさせる舞台だった。アンドレイ・シェルバンの演出は2005年にプレミエ上演された舞台で、まだ若きガランチャがシャルロッテを歌い、マルセロ・アルバレスのウェルテル、31歳のフィリップ・ジョルダンが指揮した人気プロダクションで、DVDでも発売されている。ちなみに『ウェルテル』は、1892年にウィーン国立歌劇場で独語初演された、ウィーンが誇る伝統の作品なのだ。大きな菩提樹が茂る庭が背景になっている舞台では、これまでヨナス・カウフマン、ロベルト・アラーニャ、最近ではバンジャマン・ベルナイムもウェルテルを歌っている。今回はメトロポリタン歌劇場(MET)のスター、マシュー・ポレンザーニがウェルテル、同じくMETのスター、ケイト・リンゼイがシャルロッテという配役だった。
ド・ビリーは昨年末にウィーン国立歌劇場の名誉会員に選ばれた同歌劇場とゆかりの深い実力派指揮者。フランス人でもあり、マスネはお得意の作曲家で、独自の解釈での音楽づくりとなった。まず、メランコリックな序曲から、第1幕第2幕と甘美にオーケストラを歌わせ、ウェルテルの繊細な心情と苦悩を表現する。しかし後半、第3幕からは演奏が緊迫感を増し、まるでワーグナーを想わせるようなドラマティックな演奏に変わる(マスネは若いころ、ワーグナーの影響を強く受けている)。第4幕への間奏曲は激しい感情表現で、ウェルテルの絶望を表現する。ド・ビリーの指揮は、繊細さと甘美さ、激情と緊迫感を併せ持つ、ニュアンス豊かな演奏だった。
10月のウィーン国立歌劇場日本公演では伝統(『ばらの騎士』)と革新(『フィガロの結婚』)というこの歌劇場の特徴を体現する絶好の機会となる。同歌劇場の音楽監督フィリップ・ジョルダンは、パリ・オペラ座とウィーン国立歌劇場の2つの大歌劇場で充分な経験を積み、いまや円熟の境地に到達しつつある、聴きどきの旬の指揮者。そしてベルトラン・ド・ビリーはオペラを知り尽くした巨匠指揮者。どちらも、ウィーン国立歌劇場管弦楽団の芳醇な音色が演奏に輝きを添える。
取材・文:石戸谷結子(音楽評論家)

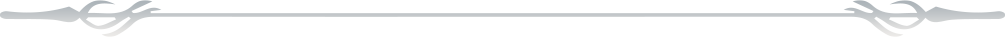
指揮:ベルトラン・ド・ビリー
演出:バリー・コスキー
10月5日(日)14:00 東京文化会館
10月7日(火)15:00 東京文化会館
10月9日(木)18:00 東京文化会館
10月11日(土)14:00 東京文化会館
10月12日(日)14:00 東京文化会館
[予定される主な出演者]
アルマヴィーヴァ伯爵:アンドレ・シュエン
伯爵夫人:ハンナ=エリザベット・ミュラー
スザンナ:イン・ファン
フィガロ:リッカルド・ファッシ
ケルビーノ:パトリツィア・ノルツ
演奏:ウィーン国立歌劇場管弦楽団
指揮:フィリップ・ジョルダン
演出:オットー・シェンク
10月20日(月)15:00 東京文化会館
10月22日(水)15:00 東京文化会館
10月24日(金)15:00 東京文化会館
10月26日(日)14:00 東京文化会館
[予定される主な出演者]
陸軍元帥ヴェルテンベルク侯爵夫人:カミラ・ニールンド
オックス男爵:ピーター・ローズ
オクタヴィアン:サマンサ・ハンキー
ファーニナル:アドリアン・エレート
ゾフィー:カタリナ・コンラディ
演奏:ウィーン国立歌劇場管弦楽団
―平日料金
S=¥79,000 A=¥69,000 B=¥55,000
C=¥44,000 D=¥36,000 E=¥26,000
サポーターシート=¥129,000(S席+寄付金¥50,000)
U39シート=¥19,000 U29シート=¥10,000
―土日料金
S=¥82,000 A=¥72,000 B=¥58,000
C=¥47,000 D=¥39,000 E=¥29,000
サポーターシート=¥132,000(S席+寄付金¥50,000)
U39シート=¥21,000 U29シート=¥13,000
