

|

|
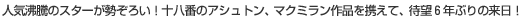
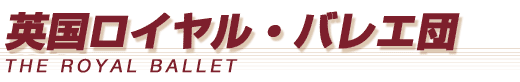 |
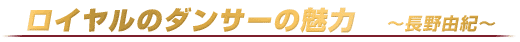 |
|

 ロンドンに住んで楽しいことの第一は、ロイヤル・バレエがそこにあること。そして悩ましいことの第一が、この作品は誰で見ようかと、いつも予定表を前に長考を強いられることだろう。シルヴィ・ギエム、ダーシー・バッセル、吉田都、そしてジョナサン・コープといったヴェテランが一晩ごとにその舞踊生命を賭けるかのような至芸を全開にする一方で、今まさに上り坂にある、あるいは絶頂期に差しかかった次の世代のダンサーが次々と成功を収める。それも「着実に育っている」といったおとなしいものではなく、すでに華々しいまでの個性の競演といった感があるのだ。 ロンドンに住んで楽しいことの第一は、ロイヤル・バレエがそこにあること。そして悩ましいことの第一が、この作品は誰で見ようかと、いつも予定表を前に長考を強いられることだろう。シルヴィ・ギエム、ダーシー・バッセル、吉田都、そしてジョナサン・コープといったヴェテランが一晩ごとにその舞踊生命を賭けるかのような至芸を全開にする一方で、今まさに上り坂にある、あるいは絶頂期に差しかかった次の世代のダンサーが次々と成功を収める。それも「着実に育っている」といったおとなしいものではなく、すでに華々しいまでの個性の競演といった感があるのだ。
その中でもひときわ品性が高く、可憐な容姿と輝かしいテクニックに恵まれたバレリーナが、アリーナ・コジョカルだ。ルーマニアの首都ブカレストの出身で1999年に入団。その後、群舞から最高位のプリンシパルへの階段を、わずか二年ほどで一気に駆け上がった。どのような複雑なステップも余裕をもってこなし、シャープでありながら同時にまろやかさを感じさせる。あたかもその全身から音楽があふれ出してくるかのようで、役作りにも「この人ならでは」と思わせる小さな、けれども決定的なデリカシーがあふれている。
 作品ごとの鮮やかな変貌ぶりも彼女の大きな魅力だ。『眠れる森の美女』で、ほのかに紅色を帯びたバラの花が全開になるのを目撃したと思わせたその次には、『マイヤリング』の皇太子の情婦として別人のように大胆・妖艶な姿態を見せる。昨年はパリ・オペラ座へ十八番の『ジゼル』で招かれ、またニジンスキー賞の女性舞踊手部門の受賞者に選ばれるなど、いまや英国だけでなく世界に認められたバレリーナだ。
作品ごとの鮮やかな変貌ぶりも彼女の大きな魅力だ。『眠れる森の美女』で、ほのかに紅色を帯びたバラの花が全開になるのを目撃したと思わせたその次には、『マイヤリング』の皇太子の情婦として別人のように大胆・妖艶な姿態を見せる。昨年はパリ・オペラ座へ十八番の『ジゼル』で招かれ、またニジンスキー賞の女性舞踊手部門の受賞者に選ばれるなど、いまや英国だけでなく世界に認められたバレリーナだ。
そのコジョカルと多くの作品で共演し、互いの魅力を最大限に引き出す素晴らしいパートナーシップを見せているのがヨハン・コボーだ。男性舞踊手の宝庫ともいわれるデンマークの出身。俳優一家の生まれでバレエを始めたのは16歳と遅かったが、その切れ味鋭い脚さばきやエネルギッシュな跳躍は、同国の誇るブルノンヴィル・テクニックの正統派の極みともいうべきものだ。演技力も幅広く、マクミラン作品の陰影のある人物造形で圧倒的な悲劇を描くかと思えば、アシュトンのバレエのコミカルな役もセンスよくこなす。
ロイヤルへの入団はコジョカルと同じく99年だが十歳ほどの年齢差があり、その包容力が彼女の才能の開花をさらに大きく促したという側面もあったろう。ともに脂が乗り切った今、カンパニーを代表するスター・カップルに成長した。
|
|
|
|

 英国ロイヤル・バレエがその輝かしい歴史のなかで最も誇ってきたものに、絵に描いたようにお似合いの看板カップルの存在がある。対照的な個性の結びつきが独特の化学反応を生むと讃えられたマーゴ・フォンテインとルドルフ・ヌレエフ。逆に、双子のようにそっくりと言われた、カンパニー生え抜きのアントワネット・シブリーと元芸術監督のアンソニー・ダウエル。レスリー・コリアとマーク・シルヴァー、ヴィヴィアナ・デュランテとイレク・ムハメドフといったあたりも、古くからのファンには懐かしい名前だろう。 英国ロイヤル・バレエがその輝かしい歴史のなかで最も誇ってきたものに、絵に描いたようにお似合いの看板カップルの存在がある。対照的な個性の結びつきが独特の化学反応を生むと讃えられたマーゴ・フォンテインとルドルフ・ヌレエフ。逆に、双子のようにそっくりと言われた、カンパニー生え抜きのアントワネット・シブリーと元芸術監督のアンソニー・ダウエル。レスリー・コリアとマーク・シルヴァー、ヴィヴィアナ・デュランテとイレク・ムハメドフといったあたりも、古くからのファンには懐かしい名前だろう。
現在は、前回取り上げたアリーナ・コジョカルとヨハン・コボー、そして二度目の出産から見事な復帰を果たしたダーシー・バッセルとジョナサン・コープの二組が、ダンサーとしての各人の実力の点でも、舞台上で男女の結びつきの強さや相互理解という点でもその伝統を受け継ぐ存在といえるが、ここへきてさらに一組、清新なカップルの誕生の気配がある。ロベルタ・マルケスとイヴァン・プトロフだ。この冬は、バレエ団の看板ともいえるフレデリック・アシュトン振付の『シンデレラ』『リーズの結婚』にそろって初主演。芸術監督以下が若い二人に寄せる期待のほどをうかがわせた。
女性のほう、ロベルタ・マルケスはブラジルの出身。リオ・デ・ジャネイロで活躍中に『眠れる森の美女』、ロシア公演の際の『白鳥の湖』などでロイヤル・バレエの舞台に登場していたが、今シーズン(2004-05年)から、正式にプリンシパルとして入団した。
小さな頭と愛らしい顔立ち。長い首から豊かな胸にかけての女性的な魅力。表現力に富む腕とすんなり伸びた脚線、とりわけ、しなやかなラインを描く膝下からつま先にかけての美しいライン。マルケスは、およそ人がバレリーナに望む身体的な条件のすべてを持ち合わせているといっていい。小柄だが(というのがまた伝統的に、古典バレエの主役として好まれてきたところでもある)、プロポーションがよいので舞台では実際より大きく見える。テクニックもしっかりしていて、たとえば『シンデレラ』の第一幕の、箒を持っての二回転のピルエットなども余裕をもってこなし、その間、彼女の大きな魅力である可憐な笑顔がかたときも損なわれることがない。
 一方のイヴァン・プトロフは、名前から察せられるようにスラヴ系の、ウクライナ出身のダンサーだ。前述のコジョカルと同じくキエフの舞踊学校でバレエを学び、彼女より二年早くローザンヌ国際バレエ・コンクールで賞を取ってロイヤル・バレエ学校に留学。卒業後すぐに入団し、2002年、わずか四年でプリンシパルの地位に上りつめた。同年の夏に吉田都のグループ公演で来日したときにはまだ若く未完成との印象を受けたが、その後実力を蓄えて、『ジゼル』『ドン・キホーテ』『ラ・バヤデール』といった古典名作や、バランシンの『放蕩息子』といったカンパニーの主要レパートリーの主役を手中にしている。 一方のイヴァン・プトロフは、名前から察せられるようにスラヴ系の、ウクライナ出身のダンサーだ。前述のコジョカルと同じくキエフの舞踊学校でバレエを学び、彼女より二年早くローザンヌ国際バレエ・コンクールで賞を取ってロイヤル・バレエ学校に留学。卒業後すぐに入団し、2002年、わずか四年でプリンシパルの地位に上りつめた。同年の夏に吉田都のグループ公演で来日したときにはまだ若く未完成との印象を受けたが、その後実力を蓄えて、『ジゼル』『ドン・キホーテ』『ラ・バヤデール』といった古典名作や、バランシンの『放蕩息子』といったカンパニーの主要レパートリーの主役を手中にしている。
ダンサーとしての彼の魅力は、端正なポーズから繰り出される切れ味のよい足技、大胆かつしなやかな跳躍にある。そこに、若いスター特有のちょっと不遜な表情が加わって、じつに王子らしい王子の姿が立ち現われる。マルケス演じるシンデレラの笑顔にとろかされるようにしてクールなプトロフが頬を寄せる姿は、今回の来日公演でも屈指の「絵になる場面」であるに違いない。
|
|
|
 |
| |
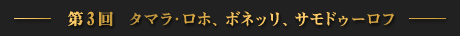
 これまで2回にわたってご紹介してきたとおり、現在の英国ロイヤル・バレエには外国籍のダンサーも多い。多文化の影響が英国の伝統的なレパートリーを活性化しているのは間違いないが、今回はさらに3人、イギリス以外の出身のダンサーを取り上げたい。 これまで2回にわたってご紹介してきたとおり、現在の英国ロイヤル・バレエには外国籍のダンサーも多い。多文化の影響が英国の伝統的なレパートリーを活性化しているのは間違いないが、今回はさらに3人、イギリス以外の出身のダンサーを取り上げたい。
スペイン出身のタマラ・ロホはじつに個性的なバレリーナである。個性的な、という形容がダンサーにとって必ずしも賛辞といえるのかどうか、ためらいがないわけではないのだが、やはりロホを語ろうとして真っ先に思い浮かぶのは、この言葉なのだ。この10年ほどでいっきに長身の団員の増えたロイヤル・バレエにあって非常に小柄。比較的ふっくらとして筋肉を感じさせない身体も、現代のバレリーナの一般的なイメージからは少し違っている。日本では2003年夏の世界バレエフェスティバルでの難技を意のままに盛り込んだ回転の印象が強く、まずはテクニックの人と受け止められているが、本人が得意にしているのはむしろ劇的な作品である。
いったいに、ロホは調子がよいときほど顔の表情を変えない。もちろん場面に応じた変化はあるが、それはいわば「従」にあたるもの。彼女のドラマ表現の格はなんといってもその視線で、くりくりと輝いたかと思うと、茫洋とかなたに投げる。その絶妙な変化が、意図的に抑えた白い面差しに、ひいては全身に、強烈なキャラクターを与えるのである。
イタリア出身のフェデリコ・ボネッリは、颯爽とした現代的な雰囲気と、王子役にふさわしい洗練された物腰をあわせ持った、オールラウンドなダンサーである。端正な面差し、恵まれたプロポーション、そしてなによりその美しい脚線がしなやかに空を切るさまは、あらゆる観客の目をひきつけずにはおかない。
2003年秋にオランダ国立バレエから移籍。その一年後に男性舞踊手の休演が相次いだ時期に、ボネッリはじつに頻繁にピンチヒッターを務めた。『眠れる森の美女』からアシュトンの長尺の一幕作品『ダフニスとクロエ』まで。だがその多忙な日々が、いわばコヴェント・ガーデンの床と彼の両足を一気に親しませることになった。その健闘ぶり、真摯な姿勢、そして何よりも高い水準のパフォーマンスによって、地元のファン、そしておそらく団員の間にも、見る間に「うちのプリンシパル」のステイタスを確立したのだった。
もう一人のヴィヤチェスラフ・サモドゥーロフはいかにも芸術家肌の、いわば一家言あるバレエ通を唸らせるタイプである。ロシアのマリインスキー・バレエで新鋭プリンシパルとして活躍した後、2000年にオランダ国立バレエに移籍。そこでレパートリーを広げ、2003年、ボネッリとともにロイヤル・バレエのプリンシパルに迎えられた。
サモドゥーロフの一番の魅力は、鋭く繊細な音感と、弾力と精度にすぐれた動きで音楽をもののみごとに使い切るところにある。昨年秋に部分復刻された『悪魔の休日』のソロはセンセーショナルといっていいほどの出来ばえだったし、アシュトンの全幕バレエとしては『シンデレラ』に続いて二つ目の主演作となった2月末の『リーズの結婚』も、まずその点においてすぐれていた。つまりは、これさえあれば世界中のどんな作品でも踊りこなすことができるという資質の持ち主。そのサモドゥーロフが他でもないロンドンを活動の場に選んだことは、観客にとってじつに幸せなことである。
|
|
 |
| |
|
|